「極楽通信・UBUD」
バリ島滞在記「ウブドに沈没」
■7月・11) 常連の集う屋台
ある時期、日本人ツーリストが溜まる屋台があった。
ミユキ(仮名)という日本人女性のバリ人の恋人が、友人と経営している屋台だ。恋人のアグン・ライは、鶏ガラのように痩せ、しばしばフラフラと姿を消すところからアンギン(風)と呼ばれている。アグン・ライは、アナッ・アグンの称号で呼ばれるカーストの一族で、先祖は王族か貴族になる。
バリのカーストは現在、称号と言葉の違いが残っているだけだ。言葉の違いは、インドネシア語もままならないわたしには、まったくわからない。
ミユキたちの屋台に店名はない。もっとも仮設テントの屋台で店名をつける必要もないだろう。
ミユキの屋台に顔を出すようになったのは、こんなことがあってからだ。
テンペゴレンで醜態をみせた後遺症が残っている次の夜。それまで毎日のように通っていた道路側に最も近い屋台を避けて、ほかの屋台のノレンをくぐった。実際にはノレンはないが、屋台はそんな雰囲気を持っている。
あと少しでメニューの料理をすべて制覇できる。今夜は、昨夜のような失敗はしたくない。どんな組み合わせでも、あの時以上の恥ずかしい事態にはならないだろう。
インドネシア料理の屋台は、どこも同じようなメニュー。
わたしはメモ用紙に「◯◯◯◯ゴレンとナシプティ(ご飯)」と書き込んだ。インドネシアにはゴレン(揚げ物)料理が多いようだ。
どんな揚げ物が出てくるか、期待と不安でいっぱいだ。
テーブルの向こう端に座っている日本人女性のわたしを見る眼が気になる。まさか昨日の再演はないだろう。テンペゴレンとご飯の組み合わせを上回る悲惨な状態になるはずはない。しかし、彼女の視線がわたしを不安にさせる。背筋が寒くなるような予感がした。
料理が運ばれてきた。
わたしは、眼の前の料理を凝視した。
盛りつけられた料理を見て、思わずわたしは、それを隠そうとした。犯罪者にもなった気分で、まわりを見渡した。誰もわたしをとがめようとしない。それはそうだ、わたしが何をどう食べようが、本人の自由だ。
それにしても、これは何だ。皿の上には、キツネ色に揚がった物体がのっている。
どう見ても、芋のフライだ。わたしがオーダーした “クンタンゴレン” は、フライドポテトだった。
わたしはフライドポテトとご飯を頼んでしまったのだ。これは、笑って誤摩化すこともできない。フライドポテトとご飯では、食も進まない。勇気を奮って、前に食べたことのあるサユールヒジョウを追加注文した。
勇気を奮ったおかげで、昨夜、のような醜態をさらすことはなかった。こんなことなら、テンペゴレンの時も素直に追加注文すればよかったと後悔している。自分の見栄っ張りな性格がつくづく嫌になる。
腹も落ち着き、一服していると、テーブルの向こう端から日本人女性が話かけてきた。
「妙な注文をする人だなと思って見てました。あなたはちょっと変な人なのですか?」
これがミユキとの出会だ。
実は彼女と知り合えたおかげで、わたしのウブド長期滞在が可能になったと言ってもよい。
こんな風にしてメニューを網羅していったわたしは、最後には、ナシゴレン1本に落ち着いた。どちらかというと味音痴で粗食。おまけに、食べることに欲のないわたしは、毎晩ナシゴレンを喉に流し込むことになった。
陽がとっぷりと暮れた8時から9時頃が、ミユキの屋台に常連が集まってくる時間帯だ。
毎晩ナシゴレンを食べながら、くだらないことを駄べるだけのことだが、いつもの時間にミユキの店へ行かないと、1日が終わらないような気持ちになっていた。
室内の薄暗い電球の明かりでは本も読めなくなり、手持ちぶさたになった頃、常連たちの足は自然と屋台街のミユキの屋台へ向いてしまう。
滞在日数の少ないわたしは、初めのうち転校生にもなった気分で緊張していた。年長者だったわたしは、そのうち屋台の牢名主的存在になっていた。
元ミュージシャンの由美さん、バリ島を研究している早稲田大学院生の西村さん、ニアス島をこよなく愛する建築家マナビー、イラストレーターの山根さん、ドイツ人青年のステファン君、世界中を旅している道木さん、バリ舞踊を習っている椰子の木あっこちゃんとまみちゃん。この頃の日本人長期滞在者は、踊りを習っている人が多かった。それも女性がほとんどだ。
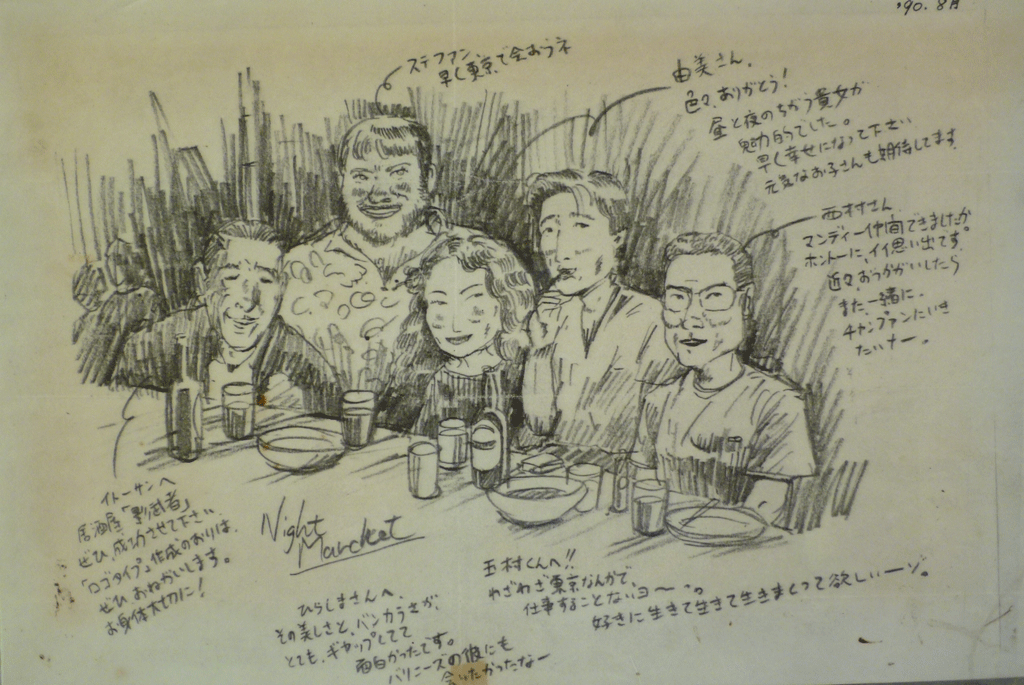
イラスト:山根さん
わたしは、ミユキに「ウブドの無責任男」と呼ばれている。命名の理由はわからない。ミユキの毒舌にタジタジすることが多いが、そんなレッテルを貼られるほど、いいかげんな奴なのだろうか。離婚の経験も今の日本では珍しいことでもない。そのほかのことで、無責任と言われる原因があったのか。人生をなめているようなところがあるが、それを言っているのなら的を得ているかもしれない。
時には、地元の著名人であるシルビオ・サントーサ氏が加わることもある。
バリが好きで住み着き、ウブド村営観光案内所を開設したジャワ人で、バリ・パス・フィンダーという地図を出版している人物だ。屋台街運営にも、彼が一役かっているようだ。
ウブドのツーリズムが始まると同時に、ツーリストと村人との間で金銭的なトラブルが頻発した。トランスポートやツアーの料金が一定していない時代のこと、シルビオは問題解決の手段として《ヴィナ・ウィサタ観光案内所》で料金の均一化を図った。(1989年6月、6年あまり続いた活動は閉鎖され、その後、村営の観光案内所へと変わった)
いつも強い地酒を飲んで酔っぱらっているシルビオが、ことウブドの観光化の弊害やバリのヒンドゥーの宇宙観に話題がのぼると「酒を飲む時くらいリラックスしたい」といいながら真剣に話してくれる。
屋台は、単に胃袋を満たすだけでなく、現地の人たちと気さくに楽しく会話ができる社交場でもあった。その土地の生活や文化、人々を知り、感じるには最適の場所だ。
年齢、経歴、価値観のまったく違う面々が、狭い屋台の汚いビニールクロスの上でかわす会話は、変化の少ない長期滞在者にとって日常の中の刺激となる。
「袖すり合うも他生の縁」なんて、都会ではとうの昔になくなってしまった言葉もここではまだ通用していた。
今日の出来事を報告しあったり、新たな情報を交換したり、新顔のツーリストが混じると彼らのユニークなアジア紀行のようすを聞いた。新顔はあらたに常連となる。数少ない旅人との出逢いは、目的意識が似ているからか心を開いた会話になりスピルチャルな関係になる。時には、短い期間で互いの内面をさらけだすように、シリアスな話にもなる。
長期滞在の面々は横のつながりでもって、ゴシップじみた噂話に花を咲かせたこともある。やはり、その手の話題は一番の関心のマトだ。日本人同士のカップルもできた。ウエスタンの恋人ができた人もいた。
カルタを頭にした弟子たちバリ人青年の色っぽい目線に落ちて行く日本人女性も多数いた。山田詠美の「熱帯安楽椅子」に、“ウブドには孕ませる空気がある” と書いてあったと記憶するが、まさに屋台街にはそんな濃密な空気が流れていた。
激しいスコールが降ったり、身体の具合が悪かったりして、ミユキの屋台に行かなかった夜があったとしよう。
翌晩、顔を出すと「昨夜は何をしていた」「いいレストランで食べたのか」「さてはPacar(恋人)ができたな」などと質問攻めにあう。長期滞在者の妙な連帯感で、一晩でも顔を見ないと心配したものだ。実際に、何日も顔を見せない人が病気だったことがあり、みんなで見舞いに行ったりもした。
常連たちを募って、山間部にあるブドゥグルの植物園に遠足に行ったこともあった。州都デンパサールの冷房のきいたレストランで、洗練された接客にみんなで驚いたこともあった。ある時には、ガムラン・ジェゴクをチャーターし、西部バリのジュンブラナ県までベモに乗って鑑賞に行ったこともあった。
ある日、道木さんが一人の日本人のご夫人から誘われて、ペネスタナン村に別荘を持つそのご夫人のお宅で「山城組」というヤクザのような名前のグループがバリ舞踊をチャーターしたので見に行こうということになった。個人宅でバリ芸能をチャーターするなどという贅沢なことができるなんて、と、憧れ半分、野次馬半分で、声をかけた滞在者が次々と「わたしも行く!」と参加を表明し、結局10人近い滞在者で押しかけることになった。
ご夫人は、もと東京のインドネシア大使館にお勤めだったイサック氏の奥様だと、その時に知った。チャーターしたグループは、芸能・山城組という芸能関係の研究グループだというのも、後から知った。この時のバリ舞踊演奏は「ティルタ・サリ」。バリ芸能をまったく知らなかったわたしには、オイリーと呼ばれる少女の踊りだけが印象に残っている。
ここでの知り合いは、一過性の友人だ。すべてが旅人だ。いつかは母国に帰るか、旅を続けるためにどこかへ行ってしまう。今までの常連が旅立ち、次の日から顔が見られなくなってしまう。次から次へ人と出会っていく。そして次から次へ別れていく。再会を誓いはするが、2度と会うことのないかもしれない旅行者との別れは少し感傷的になる。こんな時わたしは、はしだのりひこの「悲しくてやりきれない」を口ずさんでいた。誰の耳にも届かないわたしの歌声は、虚しく空を彷徨っている。
朝市は、活気ある騒然とした風景だ。
儀礼に使われる色とりどりの花や椰子の葉でこしらえた供物などの露店が並び、かぐわしい匂いを発散している。匂いを満喫しようと、鼻ピクピクさせて幾度も吸い込んだ。奥には、旬の果物が山積みになって売られている露店が軒を連ねている。
常夏の島で、旬の時季というのも妙な話だが、果物によっては収穫時季が異なる。バナナ、パパイヤ、パイナップルなどは年中ある果物だが、果物の王様ドリアンと果物の女王マンゴスチンは雨季の果物だ。果物の豊富な季節は雨季で、乾季の今は種類が少ない。
早起きの苦手なわたしが覗く10時頃には、肉や魚などの露店はもう退散したあとだ。わたしが覗く頃まで残っている魚は、干上がったカピカピ肌を見せ鮮度が著しく落ちている。氷もなく、もちろん冷蔵設備のない青空市のこと、早朝に買うことが強いられる。
昼すぎになると、今まで朝市があったことが嘘のように広場はきれいに掃き清められゴミひとつなくなる。
広場の片隅に、駄菓子と雑貨の店が開店していた。
雑貨屋を背にして広場を見るようにして、長椅子に腰をおろした。コーヒーでも飲もうか。奥にいるおやじに「コーヒー」とひとこと叫んだ。通じていないようだ。ジェスチャーで飲む振りをすると、おやじは理解できたようで「コピ」と叫んだ。わたしは「コピ・バリ」と叫び返した。
時々、砂塵の舞い上がる広場は、マカロニウエスタン(イタリア製ウエスタン映画)の寂しい町のシーンを想像させる。
雑貨屋の裏の崖が、ゴミ捨て場になっていて匂いが鼻につく。
そろそろ陽が落ちるかと思われる頃になって、長い大きなテーブルをのせた台車が広場にやってきた。次から次へと運ばれてくる。台車の位置は決められているのか、それぞれは位置につくと、テーブルやら椅子やらの荷物を降ろし始める。
屋台は組み立て式になっていた。細い6本の木の柱に細い横木が手際よく組まれ、その上をビニールシートでおおって出来上がり。ケロシンランプを横木に吊り下げ、長椅子がテーブルの両側に並べられた。30分ほどで、屋台は完成していた。
テーブルにビニールクロスを掛け、中央に飲料水のボトルを並べる。調理のためのコンロが用意され、厨房も完成。道から奥に向かって一列4軒ほどの屋台が連なる。
こんなビニールシート屋根が4列、広場いっぱいに櫛状に並び集合屋台に変身する。これがウブドの夜の屋台街だ。
※ウブドの屋台街(センゴール)は、1989年〜1993年11月22日までの4年間存在した。今、鉄筋2階建のショッピング・センターと駐車場になっている。
つづく














